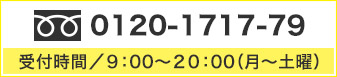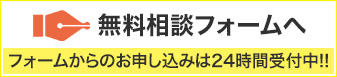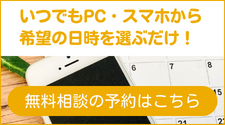トップページ > 死因贈与契約について
死因贈与契約について
死因贈与契約とは何か
「死因贈与」契約とは、贈与者の死亡により効力を生じる生前の贈与契約をいいます。死亡によって効力が生じるという点で遺言による贈与である「遺贈」と似ていますが、「遺贈」は、受贈者の意思に関係なく贈与者の一方的な意思により行える(単独行為)のに対し、「死因贈与」は契約なので、成立するには贈与者と受贈者の意思の合致が必要です。ただし、死因贈与と遺贈には共通点があるので、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。
なお、死因贈与は贈与の一種ではありますが、相続で財産を取得するケースに似ているので、贈与税ではなく相続税が課税されることになります。
死因贈与と遺贈の比較
<共通点について>
| 遺贈 | 死因贈与 | |
|---|---|---|
|
受贈者の死亡 |
遺言の効力が発生する前に受遺者が死亡した場合、効力を生じません。(民法第994条) |
民法第994条が準用され死因贈与も効力を生じません。 |
| 撤回 |
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法第1022条) |
死因贈与による処分の場合は、遺贈の場合と同様、贈与者の意思を尊重しなければならないという理由から判例も「民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されるべきである」としています。 |
| 遺言執行 |
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができます。(民法第1010条) |
遺言執行者の選任に関する規定(民法第1010条以下)が死因贈与に準用されるかについては、判例でも意見が分かれていますが、受遺者の利益保護と遺言者の最終意思の実現という遺言執行者制度の趣旨から死因贈与にも準用されるべきだと考えられています。 |
|
遺留分侵害額請求 |
遺留分権利者及びその承継人は、 遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができます。(民法1031条) |
死因贈与によって遺留分を侵害されたような場合にも、遺贈による遺留分の侵害の場合と同じように、遺留分権利者の保護という観点から遺留分侵害額請求の対象になります。 |
| 無効 |
公序良俗に反する遺贈は無効です。 |
契約なので、他の契約と同様に取り消し事由や無効事由により効力を失います。また、公序良俗に反する死因贈与も無効です。 |
<相違点について>
| 遺贈 | 死因贈与 | |
|---|---|---|
| 方式 |
法定の遺言の方式に従わなければすることができません。 (民法第960条) |
契約でありその方式に定めはないので、遺言の方式に従う必要はありません。 |
| 能力 |
15歳に達した者は、単独で遺言をすることができます。(民法第961条) |
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。(民法第5条) |
| 承認・放棄 |
遺贈の承認・放棄に関しては、相続の承認・放棄に関する規定 (包括遺贈)や民法第986~989条(特定遺贈)が適用(準用)されます。 |
死因贈与は契約なので、贈与者と受贈者の意思の合致に基づいて締結されます。そのため、相続の承認・放棄に関する規定(民法第915条以下)は適用されません。 |
|
書面によらない贈与 |
遺贈は遺言による贈与なので、法定の方式に従わなければならず、原則書面によってなされなければなりません。 |
死因贈与には方式の定めはないので、書面による必要はありません。なお、書面によらない贈与は履行の終わった部分を除き、いつでも撤回ができるので (民法第550条)、各当事者(相続人・ 相続財産管理人など)は、贈与者が生存中、死亡後を問わず書面によらない贈与であることを理由として、死因贈与を撤回することができます。
|