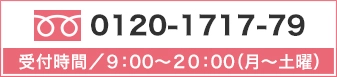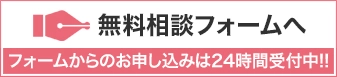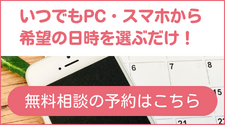トップページ > どう対応すべき?相続財産が少ない場合の手続きについて
どう対応すべき?相続財産が少ない場合の手続きについて
相続発生と同時に、相続税申告に向けてさまざまな手続きを行うことになります。しかし、もし財産が少なかった場合は、異なる対応が必要になるのでしょうか。ここでは、相続財産が少なかった場合の手続きについて説明していきます。
相続手続きを必要とする基準
被相続人から財産を相続した際、その財産は相続税の課税対象となります。ただし、相続財産が次の算定式で求める基礎控除額より少ない場合、相続税非課税となり申告手続きは不要です。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続財産を4,000万円、相続人が3人とした場合について考えてみましょう。基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となることがわかります。相続財産は4,000万円であり、基礎控除額の方が金額的に高いため、相続税非課税として扱われるのです。
仮に相続財産が5,000万円相当だったとしても、相続税の課税対象額は200万円まで下がりますので、相続人の税負担はある程度抑えられるでしょう。
相続財産が少なった場合の手続き
相続財産が少なかった場合でも、遺産分割協議や不動産の相続登記は行わなければなりません。
遺産分割協議書を作成する
現金や預貯金、有価証券などの財産が少なかったとしても、相続する財産がある以上、遺産分割協議を行い、財産の引き継ぎ方について決定する必要があります。また、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成しなければなりません。
財産の多少に関わらず、相続税申告に関する手続きが不要となるのは、相続人が1人しかいない場合や基礎控除額より財産評価額の方が低かったケースなどに限られます。プラスの財産がある場合は前述の通り遺産分割協議書の作成や相続税申告手続きが必要になりますし、マイナスの財産が多かった場合で相続放棄を選択した場合は所定の手続きを行わなければなりません。
不動産の相続登記を行う
相続財産に不動産が含まれていた場合は、遺産分割協議により「誰がどのように不動産を相続するか」を決める必要があります。協議の結果、不動産を相続することになった相続人は、必ず相続登記を行わなければなりません。「その土地が誰のものか」を明確にするための手続きであり、登記を済ませて初めて売却や運用などが可能になるのです。
特に、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記が義務となり、過去分に遡って対処することが求められるので、忘れず手続きすることが大切です。
特例を受けて非課税になった旨を申告する
配偶者の税額の軽減や小規模宅地の特例などを適用した結果、相続税が非課税になった場合は、その旨を税務署に申告する必要があります。専門家に相談し、正しく申告を行いましょう。
相続財産が少なくて揉める可能性
相続財産が少なくても、財産がある以上、揉め事の発生は否定できません。揉め事に発展する前に専門家に相談し、スムーズな手続きを実現することをお勧めします。
相続財産が不動産しかない場合
現金や預貯金、有価証券など分割しやすい財産がなく、遺されているのが土地や建物しかない場合、相続人の間で揉める可能性が出てきます。不動産は容易に分割できないものですが、相続人の誰かが不動産を引き継いでしまうと、他の相続人が得る財産がなくなるからです。
このようなときは、代償分割や換価分割による相続が無難です。
【代償分割】不動産を相続する代わりに、法定相続割合に基づく金銭を他の相続人に渡す方法
【換価分割】不動産を売却して現金化し、法定相続割合に基づいて分割する方法
借金などのマイナスの財産が多かった場合
被相続人が遺した財産のうち借金を含むマイナスの財産が多かった場合は、相続人それぞれが頭を悩ませるかもしれません。
このようなときは、マイナスの財産とプラスの財産のバランスを考えながら、限定承認もしくは相続人全員での相続放棄を選択するのも一案です。ただし、いずれも他の相続人が不利益を被らないよう十分な話し合いが必要になりますので、慎重に事を進めた方がいいでしょう。
まとめ
相続財産が少ない場合、相続税非課税となる可能性がある一方で、相続人の間で揉めることも考えられます。相続に関する揉め事は親族間の関係性にも影響しかねませんので、相続開始とともに、適切な相続手続きについて専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では相続診断士の資格を有する行政書士を窓口とし、司法書士や税理士、弁護士との連携のもとで親身なサポートを行っております。まずは無料相談をご利用いただき、現在の状況からお聞かせください。